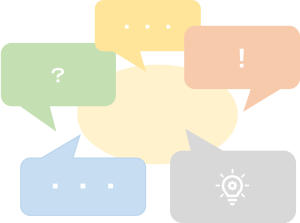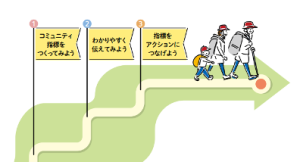日時:平成25年3月9日(土)14:00~16:30
会場:東京国際フォーラム ガラス棟会議室G510
参加人数:73名
主催者挨拶
今田克司:一般財団法人CSOネットワーク代表理事
まず今日お集まり下さった参加者の方々に御礼申し上げる。私どもの団体「CSOネットワーク」のCSOとはCivil Society Organizationの略。当団体は2004年から活動しており、海外のNGO/NPOと日本の活動をつなぐ様々な活動を行っている。本日のようなテーマに関わり始めたのは東日本大震災以降で、福島の農家、特に有機農業に携わる方々や酪農家の方々を支援する活動を始めたことがきっかけである。その中で様々な方々とつながることができ、今回のようなイベントの実施に至った。なお本事業は、独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成を受けている。昨年は、今日ご登壇される菅野さんとともに、リオデジャネイロで開催された国連持続可能な開発会議に出かけ、発信のお手伝いをした。今後もこのように海外とのつながりを持つことも視野に入れて活動していきたいと思っている。
日本の地域社会が抱える問題は、日本固有の問題ではなく、世界各国が抱える問題でもあるという認識を持っている。また、都市と農村の関係については日本の特異性もあると思うが、一方で普遍的な部分もあるのではないか。今日は、日本の特異性を踏まえた上で、普遍的な流れの部分で、私たち市民ひとり一人がどのように動いて行けばいいのかを一緒に考えるきっかけとしていただきたい。本テーマは、私たちにとって比較的新しい分野の活動であり、このシンポジウムをきっかけに今後も様々なかたちで皆様と交流を続けたいと思っている。
基調講演1 農山村と都市を結ぶ―地域と人の力
大江正章 氏:コモンズ代表、(特活)アジア太平洋資料センター代表理事
今日は「農山村と都市を結ぶ」というテーマで包括的な話と具体的な話をお伝えするが、時間が限られているため、具体的な事例についてはより詳しく書かれている著書『地域の力―食・農・まちづくり』(岩波新書、2008年)をお読みいただければと思う。
そもそも「地域」が注目されたのは1970年代後半である。当時「地域主義」という考え方が広がった。この背景には1971年のローマクラブの「成長の限界」というレポートがあり、経済成長のあり方を見つめ直さなければならないだろう、という流れがあった。それまでの経済学、つまり近代経済学やマルクス経済学のどちらにおいても「地域」はあまり顧みられてなかった。そのことがそもそも様々な行き詰まりの原因となったのではないだろうか。ほぼ時を同じくして、当時の神奈川県知事の長洲 一二さん(構造改革派のマルクス経済学の研究者)が「地方の時代」という問題提起をした。
しかし、その後バブル経済に邁進していく中でそうした発想は忘れ去られ、農山村の価値はほとんど重視されなかった。歴史学者の増田四郎さんは1985年に「地域の力」というタイトルの本を書いているが、あまり注目されなかった。私は今こそこのテーマが必要であろうと思い、冒頭で紹介した本を書いた。
今日は、今の時代をどのように捉えたらいいのか、農山村と都市というフィールドの中からものの見方を提起したいと思う。まず、「限界集落」などとよく言われるが、私は限界なのは都市のあり様だと思っている。都市は食べ物やエネルギーを自給できない脆弱さを抱えている。これは3.11後より明らかになってきた。ご存知の方も多いと思うが、日本の食料自給率は39%だが、東京都の食料自給率は1%、神奈川県や大阪府は2%、エネルギーにしても同様にきわめて低い。このことからも言えるように、都市は農山村に依存しなければ生きていけない。そうであるなら、農山村は自分たちのあり様がこれからの社会をリードしていくのだとまず認識する必要がある。それが地域力、あるいは田舎力であり、これからはそういう時代だと思っている。
過疎や人口減少ということがよく言われるが、日本中が人口減少社会に突入している。それならば人口を増加させるということよりも、自分たちの地域の魅力を増して、人に来てもらうことを考える時代である。魅力がある地域には必ず人が訪れる。農山村で人口の何十倍もの人が集まって、そこにある程度のお金を落としていく、さらには人が移り住んでいるというところがたくさんある。ひとつのキーワードは「交流人口」である。
高知県の馬路村は、人口1,000人の小さな村だが、「ゆずドリンク」で著名である。農協が中心となった「ゆずドリンク」の生産で年間33~35億円の売上を達成している。多くの人はこの数字に注目するが、こういうものを生み出している地域の存在が重要であり、そこにこそ注目すべきである。「ゆずドリンク」のCMでは、商品を宣伝するのではなく、自分たちの地域自体をアピールしている。こういう活動が今最も求められている。また「特別村民制度」を設け、年間少額を払うことによって宿泊費が安くなったり、お土産が少し安く買えたりというようなことをしている。そうして実際の村民を大きく上回る数が村を訪れている。
このようなところにはよそから人がきて定住する。いわゆるIターン、それからUターンである。私はよそ者(Iターン)、出戻り(Uターン)と呼ぶが、そういう人たちが元気なところほど地域力が増し、田舎力も増すと思っている。例えば「地域の力」でも紹介している徳島県の上勝町の人口は2,000人くらいで、高齢化率50%程度、ある意味では「限界自治体」である。しかし人口の4.5%がIターン者で、第3セクターなどで働いている。また群馬県の上野村は人口の13%がIターンだという。約180人が定住していることになる。主な仕事は農産加工業や観光業。上野村は皆さんがよくご存知の内山節さんが半分生活をしているところである。彼は、年間300万円あれば暮らせるという。そして、「年間300万の仕事を見つけるのは難しいが、30万稼げる仕事を10個見つけると考えたらどうか」と言っている。これはつまり多様性ということである。日本の農業は1961年の農業基本法以降一貫して大規模化、専業化、化学化、装置化してきたが、そうしたひとつのものだけをやるというあり様だけではなく、たくさんの小規模な仕事を組み合わせながら生計を立てていくということ。実はそうしたあり様は、これからの社会のあり方を考えるうえでは最も先進的な考え方だと思う。今までの常識を疑ってみるという頭の切り替えをしていく必要があるのではないか。
一度都会に出た人やよそから来た人のほうが、その地域の魅力に気づくことができ、またそれを外に広げるツールを持っている。それによってまた人が集まる。上勝町のリーダーはこれを「上勝好循環システム」と呼んでいる。よく地域おこしの世界で、「よそ者」、「若者」、「馬鹿者」というが、この3つが村おこしのキーワードである。そして、それを支える人間が必要であり、それこそが出戻りだと思う。彼らのように、都会に出てその良さと悪さを肌身で感じた人間が、地域に戻ってもう一回自分たちの故郷を元気にしていくカギになる。出戻りの包容力が都会と田舎を結ぶ大きな力になるといえる。
さらに「国内版フェアトレード(公正な交易)」を進める必要がある。「フェア」とは一般的には途上国の一次産品を公正な価格でもってくることをいうが、公正なモノのやりとりは日本の農山村と都市においても考えなければならない。なぜなら、これまでは決して公正な貿易ではなく、都市は農村を収奪してきたからである。例えば、お米の値段がそうである。私が大学を卒業した1980年当時、生産者の手取り価格は1俵(60キロ)16,000円だったが、2010年頃には10,000~11,000円になっている。30年間で生産者米価は昔と比較して3分の2になったということである。その間サラリーマンの初任給は1.7~1.8倍になっている。このことからも不等価交換が進み、激しくなっているといえる。農業や水産業に携わる人の取り分を明らかにしたデータでは、1970年前後には35%が生産者の取り分であったが、2000年頃にはこれが14%に下がっている。製造業の部分はあまり変わらず、もっぱら取り分が増えているのは流通産業と外食産業という構造になっている。そこでフェアなトレードを国内で考えることが必要。
CSA(Community Supported Agriculture)と呼ばれる、地域が支える農業・漁業という考え方があり、アメリカやフランスで広がっている。これは野菜や穀物などの代金を消費者が1年分前払いを行う仕組みで、労働による一部代替もある。このような取り組みに参加しているのは必ずしも裕福な消費者だけではない。日本では3.11以降、一番生産者を支えなければならないときに消費者が離れてしまった。有機農業運動はたくましい生産者を育てることには成功したが、たくましい消費者をつくることに失敗した。さらにいうとCSAという概念は本当に正しいのだろうか。私は、これからはむしろ農業が地域を支えるASC(Agriculture Supported Community)なのではないかと思う。
京都府綾部市のある限界集落では、市から若干の助成金を受けて近畿日本ツーリストと組み、神戸・大阪・京都の消費者たちを呼び込んでふきの収穫ツアーを行っている。このように自治体、行政、いわゆる公の力と民の力が一緒になった取り組み、公と民の協働が重要である。
都市の市民と農山村がつながるためには、21世紀は「第一次産業の時代」、「脱成長の時代」と我々が認識を変えることが必要である。さらに、定住の一種村人だけではなく、二種村人(近隣から通う)、三種村人(都市から通う)が融合していくこと、開かれた田舎にしていくことを考えなければならない。最後に、豊かな地域を創るためには原理主義にならず、多くの人を仲間と捉え、また市場を巻き込んでいくことが必要である。人と人のしなやかな結びつきや顔の見える関係性を築いていくことが大切だと思う。
基調講演2 自然循環の共生社会をつくる道すじ~農村と都市・市民をつなぐ実践と展望~
古沢広祐 氏:國學院大學教授、(特活)「環境・持続社会」研究センター代表理事
今私たちが生きている21世紀はどのような時代かというと「メガシティ(巨大都市群)の時代」と言ってよいのではないか。その象徴的なものに、計画発表の段階だがドバイ・シティ・タワー(2400m)や、すでに建設された世界最高の高さを誇るブルジュ・ハリーファ(828m)をはじめとして超高層の建造物が世界中にできている。
エネルギーという面から見ると、ひとり一人が大量のエネルギーを消費しながら生きており、それが限界にきているといえる。さらに我々は原発事故などといった「巨大リスク社会」に生きている。これは福島の原発事故からも明らかである。スケールの違いはあるが、事故は世界各地で起きている。現在アジアには計画を含めると100基以上の原発ができつつあり、我々は原発大陸と共に生きようとしているとも言える。石油をはじめとする主要な資源は50年以内に枯渇すると予想され、悠久の歳月の中で蓄えられてきた化石燃料が一瞬のうちに消費し尽くされている。このような社会は持続可能な社会ではない。
気候変動や生物多様性など様々な分野で国際条約や環境条約が成立していることからもわかるように、20~21世紀は大きな転換点にあるといえる。これらを通して世界は低炭素社会、そして生物と共存していく社会へ向かうべく舵を切ったのである。
都市の問題に目を向けると、世界全体の都市人口は今後さらに増加が見込まれ、特に途上国では都市部でのスラム人口の増加が懸念されている。一方、地域間で差があるため、膨張する都市がある一方で、停滞・縮小する都市もある。日本をはじめ多くの先進諸国では、もはや都市膨張に未来を描く時代ではなく、縮小していく中で未来を見ていかなければならない時代を迎えている。
食と農について重要なせめぎ合いが起きている。人間中心の生産主義がいろいろなかたちで限界に達している。これを超えていくときに、技術で乗り越えていこうという動き(ライフサイエンス主義)と、もう一度自然とのつながりを取り戻そうという方向で考える動き(エコロジー主義)とのせめぎ合いが起きている。私達の日々の命を育む食の中でも価値観、社会観の戦い「フード・ウォーズ」が起きているのである。私たちの身近なところで言うならば、ファストフード的な社会とスローフード的な社会のせめぎ合いといってもいい。
もう少し長い時間の流れで見たときに食と農における2つの展開方向は、「単一・極大化の展開方行(自然征服、排除・支配型)」と「複合・バランス調整の展開方行(共生・共存型)」の2極的な流れがせめぎ合っていると考えられる。つまり単一価値のモノカルチャー的な展開になるのか、多様性を重視した共存型になるのかということである。実は、これは私たちの心のあり方、社会のあり方、豊かさを問い直すということにもつながっている。ノーベル賞を受賞したケニアのワンガリマータイさんは、「Mottainai」を世界のこれからの新しい価値観の共通語にするべきだと述べたが、価値観の転換を示す重要な提起ではないだろうか。
食料システムという面を見ると、工業的な食料システムは、人力を激減させ安価で豊富な食料生産を実現した。それはトラクター燃料や肥料、殺虫剤、除草剤と、各種の輸送・加工の面で、多大な化石燃料に依存している。現在の食料システム(米国の場合)は人為活動による温室効果ガス排出量の20%以上となっているということである。そのような中で、「脱炭素、ローカル、資源循環型」のシステムへの移行、展開が世界で進みつつある。これは日本だけでなく、アジアや世界各地にも広がっている。
例えば米国カリフォルニア州では、種から食卓へ、そしてふたたび種へとつなぐ生命(いのち)の循環を教える菜園学習が注目されている。カリフォルニア州だけでも幼稚園から大学まで3,000以上もの学校のスクール・ガーデンで食育菜園プロジェクトが行われ、大きな効果をあげているということである。その他にもイタリアやキューバ、日本国内では埼玉県小川町など各地で様々な取り組みがある。エネルギー分野でも再生可能エネルギーの利用が広がりつつある。デンマークでは、政府が2050年に再生可能エネルギー100%を実現する戦略プランを公表している。日本ではこれからだが、市民出資の自然エネルギー事業が各地で行われている。
まとめると、今私たちの世界は大きな転換点を迎えているということである。地域の中で、あるいはローカルなものの中で、再生可能な資源やエネルギーの中で暮らすための実践が始まっている。私たちは様々な自然が産み出す多様性の恵みをもう一度大切にし、自然との関係を見直しながら産業社会を組み立てていかなければならない。
我々は未来を、グローバル化したテクノピア「科学技術依存社会」の中で生きていくユートピアとして創っていくのか、ローカルな、あるいは自然の奥深い価値にもう一度目覚めて、その中で新しい自然共生社会のあり方や生き方を創り出していくのか、大きな岐路に立っている。今日ここには、新たな道を模索しようということに関心のある方が集まっていると思う。これからどういう一歩を踏み出すかということについて、このあとのパネルでも話していきたい。
パネルディスカッション
コーディネーター:黒田かをり(一般財団法人CSOネットワーク事務局長・理事)
パネリスト:岡田芳明 氏(三菱地所株式会社 環境・CSR推進部長)
菅野正寿 氏(福島県有機農業ネットワーク 理事長)
古沢広祐 氏(國學院大學教授、「環境・持続社会」研究センター代表理事)
大江正章 氏(コモンズ代表、NPO法人アジア太平洋資料センター代表理事)
都市と農山村をつなぐ「空と土プロジェクト」
岡田芳明 氏(三菱地所株式会社 環境・CSR推進部長)
都市と農山村をつなぐ「空と土プロジェクト」は、三菱地所グループがNPO法人「えがおつなげて」と連携して山梨県北杜市須玉町増富地区で進めるプロジェクトである。増富地区は、耕作放棄率が62%、高齢化率が62%のいわゆる「限界集落」で、販売農家はゼロ、JAも撤退するという状態にあった。「えがおつなげて」は2001年2月に設立され、2003年に構造改革特区「増富地域交流振興特区」の特例措置(農地貸与許可)で、1万haの農地で活動を開始した。
三菱地所グループの基本使命は「まちづくりを通じて、真に価値ある社会の実現に貢献」、ブランドスローガンは「人を、想う力。街を、想う力。」である。2008年に始まった三菱地所と「えがおつなげて」の都市と農山村をつなぐ「空と土プロジェクト」は、CSR重点分野のひとつ「地域社会との共生」と、都市と農山村交流による「増富地区の活性化」を目指すものである。「空と土プロジェクト」は、開墾・田植え・森林体験ツアー、農薬を使わない酒米作り、山梨県産材の活用、山梨県の農産物を使ったイベント、などで構成される。
三菱地所は、グループ社員・家族、住宅事業のお客様、丸の内エリアの就業者、丸の内のシェフの参加を募り、「えがおつなげて」は地元自治体、地域住民、木材生産者と連携し、それぞれが役割を果たしつつ、互いに連携をとり、「都市と農山村がお互いに元気になる社会」を目指している。
プロジェクトには次のような継続的発展の仕組みがある。まず「空土ファーム」である。これは「えがおつなげて」が地主から農地を借り受け、日常管理を行いながら、三菱地所グループが活用するという仕組みである。次に、「ワークショップ」、「空土定例会議」、「アドバイザーミーティング」である。「空土ファーム」での体験・学びを、「ワークショップ」で振り返り・学び、毎月の「定例会議」で共有・対応・見直しを行い、さらに年1回、外部アドバイザーの意見を聞く「アドバイザーミーティング」で年度の実績・計画を客観的に評価してもらう、といった流れになっている。
ワークショップから生まれた成果のひとつに「純米酒丸の内」がある。これは「棚田に酒米を植えて日本酒をつくりたい」という参加者の声をもとに、寒冷地に適した酒米を選び、小ロット対応の地元酒蔵に製造を頼むなどして課題を解決していった。2つ目は、2008年10月に取り組みが始まった「2×4住宅建材」である。ワークショップの中で、山梨県では森林資源が十分使われないまま放置されていることを知り、国産材の活用に取り組んでいた三菱地所ホームと「えがおつなげて」が、山梨県や地元林業者に働きかけ、サプライチェーンの構築や新たな認証制度を創設といったかたちで課題を解決していった。さらに2011年8月31日には、山梨県、三菱地所株式会社、三菱地所ホーム株式会社、「えがおつなげて」で、山梨県産材の活用に関する四者協定を締結した。この他にも、自然エネルギーツアー、間伐材ファニチャーづくりツアー、親子キャンプツアー、味噌づくりツアー、丸の内での山梨県産食材フェアを実施している。
山梨県産材の木材や食材を自社グループの事業活動に結び付けることでグループにとって新たなブランド価値が創造され、事業にもプラスになり同時に地域活性化にもプラスになっている。新たな共有価値の創造(CSV: Creating Shared Value)の必要性が提唱されているが、当社の社会貢献活動はまさにこの方向にある。今後も「空と土プロジェクト」は三菱地所グループと「えがおつなげて」のパートナーシップで持続可能な社会の実現を目指して活動を継続していく。
有機農業による地域の力と市民の力による持続可能な共生の時代へ
菅野正寿 氏(福島県有機農業ネットワーク 理事長)
まず福島の現状について。原発事故の影響でいまだに福島県内に10万人、県外に6万人が避難するという異常な事態である。また住民は低線量の被ばく、内部被ばくなどの国の情報を信頼せず、科学者専門家の意見もバラバラで科学的検証がない不安を抱えている。住宅除染は進まず、森林除染に至っては手つかずの状態である。また損害賠償は遅れており、十分ではない。さらにこの損害賠償が地域を分断することにもつながっている。農業の面では、耕作放棄地が拡大しており、また作付制限指示が農家の心の制限にもなっている。
このようななか、復興の光りが見えてきたのは耕して栽培した米と野菜である。玄米の全袋検査で99.8%が25Bq/kg以下(約11,000万袋・30kg)であった。野菜はほとんどが不検出(検査限界値10Bq/kg)である。またコープふくしまの調査による食事の測定結果では検出世帯はゼロである(6~11月)。ただし、梅、栗、柿、ゆずなど(永年作物の樹木系)は今年もセシウムが移行している。山菜、きのこ(野生きのこ、原木しいたけ)は出荷制限の状態にある。
この2年間、福島県二本松市東和地域では農家、住民、大学研究者(日本有機農業学会)の共同の実態調査をすすめるなかで放射性物質(セシウム)が土中に固定化されて農産物への移行が低減されることが実証されてきた。しかも粘土質と腐植の複合体に微生物資材を活かした有機農業による営農の力がより高いことが証明されてきている。地形も気候も土壌も知っている農民と共に、大学研究者、行政による住民参加型の復興が大切であると考える。
地域づくりという面では、放射能に汚染されて、あらためて旬の食べ物の自給とエネルギーの地域自給による地場産業と雇用をつくることが新しい地域社会に求められていると感じている。これまで都市は地方に、ゴミ、基地、水俣病、そして原発を押し付けてきた。この過疎と過密という日本の構造こそ根本的に見直していかなければならない。高度経済成長時代に農村から失った地域資源を活かした加工の技(味噌、醤油、炭焼きなど)と地域分散型再生可能エネルギー(水力、風力、バイオマスなど)により地場産業を育て、働く場をつくることが必要である。今回の東日本大震災ではたくさんの市民団体の皆さんにご支援をいただいた。この市民の皆さんの力と地域の力の共生のあり方を考えていく必要がある。
つまり原発事故を転換点として農業と農村の持っている価値をあらためて見直していかなければならないと考える。農家は米や野菜をつくっているだけではなく、美しい里山も生物多様性も育んでいる生命と環境の生産者であるということ。さらに子どもからお年寄り、婦人、新規就農者や障がい者まで共に汗して働く場が農業・農村にはある。放射能汚染により地域が分断されて、あらためてこの地域コミュニティの大切さを痛感している。より人間らしいくらしのありかた、食べ物、エネルギー、コミュニティの再生は自然をいかした農村地域のなかでこそ育まれると感じている。ここに市民、企業、研究者との新しい多様な関係をどうつくっていくか。原発のない新しい時代はこの多様な市民と農村の共生のなかにあるように思う。
以下、ディスカッション(敬称略)
【黒田】東日本大震災を契機に農業にどのように変化が起きているのか。あるいはひとりひとりの関心、行動、そして国の政策についてはどうか。
【大江】震災を契機に生き方を見直す人が多くなっていると感じる。工業中心の文明のあり方ではなく、地に足のついた生き方を考え、土に関わり出した人も多い。「パルク自由学校」では今年、以前からの「東京で農業」に加えて「初めてのオーガニック」も始めたがあわせて70人以上の定員が埋まっているという状況。すぐに地方へ移住というケースは少ないが、自分の足元から暮らしを見直す動きが加速している。しかし、国の政策はそれを受け入れる方向にはないというのが事実であり、そこへ影響力を及ぼすまでには至っていない。国は「強い農業」というが、本当に「強い」農業は「持続可能な農業」、「再生産可能な農業」である。農業の今までの歴史は持続可能ではないし、強くもない。本当に強いのは生産したものを買ってくれる人、加工をしてくれる人を持っていること。生き残る農家はそういう農家であると考える。一方で、一般の農家では後継者はほとんどいない。環境を守り、持続可能で、経営も成り立つ農業を一農家が孤立してやるのではなく、地域でつながってやっていくことが重要である。
【黒田】環境問題には多くの団体が関わっている。環境と農業は関わっているようでつながっていないように見えるがどうか。
【古沢】気候変動など、問題が広がっている中で農業への影響が心配されているが、まだ個別対応という流れになっている。しかし、今後の影響を予測してトータルに対応する研究も行われている。また農業は生物多様性との関係が深く、里山保全・再生ということで、それぞれのつながりが生まれている部分もある。またすでに指摘したが、根本的に全体として変えていこうという動きも生まれてきている。
【黒田】リオの会議、生物多様性の会議にも参加した経験から、生物多様性と有機農業のつながりについてどう考えるか。
【菅野】人々は汚染されてはじめて農業と暮らしがいかに循環型だったかに気付いた。環境をつくってきたのは農民である。しかしこれまではその農民が国際的な会議に出るということはなかった。つまり、当事者を交えない環境会議であった。本来は農林漁業の人たちを中枢に据えるべきではないか。農業は多様な人が働く場であり、それを壊すような復興はいかがなものかと思う。
【黒田】モノカルチャーか共存か、共存について問い直すときが来ているのではないか。
【古沢】豊かさの価値尺度は多様である。GDPで豊かさを測っていいのか、何が豊かさかの問い直しが起きている。多様な価値、多面的な価値があり、見えている部分以上の価値があるのではないか。具体的な政策対応としては、環境税など国のレベルで制度政策的に社会の在り方を改革していくという方法もあり、また個別に地方自治体レベルで政策的に対応していく方向も生まれつつある。
【大江】環境は田んぼが生み出しているといえる。環境と農業は密接につながっている。
【黒田】プロジェクトには社員と丸の内の人が参加しているが、これに関わることであらわれてきた変化は。また企業が農山村に関わることが増えているが、どうしてなのか。そして企業はどういう役割が果たせるのか。
【岡田】参加者アンケートでは、100%の方が大変満足または満足という状況である。「癒しのプログラムである」、「これを機に田舎に帰ることを検討している」という声もある。参加者のうち女性が半分以上を占めている。もともと関心のある人が参加したことで、さらに気持ちが強化され、リピーターになっている。ワークショップを通して当事者意識も出てきた。企業が取り組む意義は、社会課題解決に本業を通じて取り組むということ。従来のCSRは儲かった分を回すということだったが、本業を通じて、共同で価値をつくっていくということが重要になってきている。これはISO26000の考え方にも合っている。
フロアからのコメント・質問
【フロア】岡田さんへ。参加した人の次のステップ、または人としての変化というものがあったかどうか、またそれを目指しているのか。
【岡田】始まって5年のプロジェクトなので、まだそこまではいっていない。OBに広げていくという意味で参加を促すなどはしている。退職後の手がかりとして参加した人もいる。今後の課題としては、より地域に密着した活動をしていきたい。そのために地元での認知度も上げる取り組みも始めている。少しずつ改善しながら地域との関わりのあり方を学んでいきたいと考えている。
【フロア】都市と農村ということで、これまでは固定観念で、都市の消費者と農村の生産者や、工業と農村と対立軸で考えられることがあった。今回は企業が中間に入ることで新しい都市と農村のあり方が提案されているということが新鮮であった。企業がなかだちすることによってよい面は。また企業側には企業の営みとし今後これをやっていく見通しがあるのか。
【大江】典型的な例は埼玉県小川町。ここではもともと有機農業が盛んであったが、地域全体(集落)が全面的に有機農業に転換したきっかけは企業。中小企業のいいところは社長のひと声で変わること。リフォーム会社の社長が余った有機米を買い取り、即金で支払った。そして希望する社員は給料天引きでその有機米を手に入れるという仕組みをつくった。こういった仕組みは他のところでも可能である。今までいくつかのNPOは企業セクターについてきちんと考えてこなかった。しかし、地方の地域に根差した企業は地域のことを考えている。そこと関わっていくのは必要なこと。そして大事なのは企業が取り組みを本業につなげていくこと。それによって企業が永続的に取り組むものになる。
【岡田】企業の評価軸が変わってきている。財務プラス自然・社会資本に対してどういう影響を及ぼしているかがかなり重要になってきている。また企業のブランド価値という面でも、社会・環境への関わりを深めることによって価値を高めることができる。儲けるだけというのは時代遅れ。グローバル企業、特にヨーロッパなどの企業は進んでいる。そういったところにキャッチアップしようということで、日本企業でも本業で正面から社会課題に取り組もうというところが増えつつある。
【フロア】菅野さんへ。これからの活動について。
【菅野】今までの企業と農家は敵というかたちはつくられたもの。3.11をきっかけに、国産材を見直すなどいろいろな取り組みが企業と農家でできる。水力発電や太陽光など、地域分散型のエネルギーを企業と地域の皆でつくっていく、さらに地域に働く場をつくることも重要。そういったかたちで過疎と過密を根本的に見直すために、企業、市民、農家が一緒に関わる転換のときがきていると思う。
【黒田】最後に皆様からひと言ずついただきたい。
【大江】福島の農産物は売れず、苦戦している。放射性セシウムが検出されない米や野菜であってもそういう状況。われわれの食べ物を作ってきた人とつながっていくことが大切。私たちは福島の生産者を応援しつつ、さらに「まちびとも耕せ」ということを伝えたい。
【古沢】従来型の中央集権的で生産と消費が切り離れている分断型産業展開ではない方向性が求められている。農林水産の第1次産業をベースに、加工・流通・販売や各種参加型事業展開などが組み合わさる、総合的・立体的に組み立てていく産業のあり方、いわゆる6次産業化という時代が始まっている。例えば古くは風土産業という考え方があり、新たに見直されつつある。
中央集権型・グローバル化の一方で、ローカルをベースに全体的な総合的な創造型の産業にシフトしていく時代が胎動しつつある。海外でも、例えばヨーロッパを中心に、ソーシャルビジネスや各種協同組合、共同事業体の連合体が生まれているし、産業の組み立て方で実験的な取り組みが模索されている。日本でも同様で、さまざまな地域的な連携をつくっていくことができる可能性がある。
【菅野】日本型食生活はセシウムを排出している。もう一度食生活を見直すときがきている。来週、下北沢にオーガニックカフェをオープンする。避難している人が集まる場にもしたいし、福島と都市を結ぶひとつの拠点にしたい。
【岡田】今、価値のせめぎあいを感じる。私たちは情報源が限られるなかで、本当の意味で一番苦労している人のことがわからずにいろいろなことをやっている部分がある。そういう意味で今日この場で菅野さんたちにお会いできたことはよかった。気づきのなかで、行動を起こしていくこと、企業が何のために事業活動をしているのか、常に考え、社会共通の価値を目指して企業も事業活動を見直していくことが大事、そのためにはネットワークをつくり一緒に歩んでいくことが大事だと改めて思った。
【黒田】今日は私たちの社会をこれからどうするかについて考えるためのたくさんのヒントをいただいた。ひとつ言えるのは、多様性が重要だということ。多用な力が連携・協力し合っていくことが地域をつくっていくのではないかと考える。