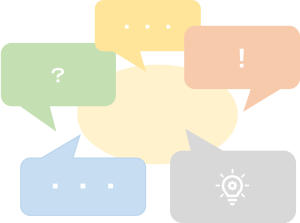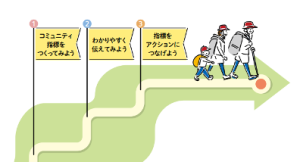日時:2014年9月6日(土)13時30分~17時00分
場所:國學院大學渋谷キャンパス、常磐松ホール
共催:國學院大學共存学プロジェクト、地域の力フォーラム委員会(CSOネットワーク)、共生社会システム学会
*本フォーラムは、一部、独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成を受けて開催されました。
開会挨拶
古沢広祐 國學院大學経済学部教授/共存学プロジェクト
3.11以降、社会のあり方、文明のあり方が変わっていくのではないかということを感じている。本日のフォーラムでは、都市と農村、有機農業といった視点から農業のあり方や地域のあり方を考えていきたい。
<第一部 特別基調報告>
星寛治氏 山形県高畠町有機農家/たかはた共生塾顧問/農民作家
「輝く農の時代へ~都市市民と共に」
ひん発する気象異変と自然災害
農の現場にいると日本列島、そして地球全体の気象の変化を実感する。1年を通して各地で「記録的」、「想定外」の自然災害が頻発している。自然と向き合う農林水産業の現場では大変な戸惑いとダメージを受けている。命に一番近い営みが、地球環境の変化によってやりにくい時代になってきたと感じている。
 日本列島は温帯であったが、もはや亜熱帯から熱帯に近づいているという実感を持っている。自然のものさしが通用しなくなり、自然の変調は植物や野生生物の変化にも表れていると感じる。これには地球温暖化、酸性雨、大陸からの大気汚染物質の飛来などが関係していると考えられる。
日本列島は温帯であったが、もはや亜熱帯から熱帯に近づいているという実感を持っている。自然のものさしが通用しなくなり、自然の変調は植物や野生生物の変化にも表れていると感じる。これには地球温暖化、酸性雨、大陸からの大気汚染物質の飛来などが関係していると考えられる。
栽培作物の適応地図も塗り替わり始めている。例えば、北陸生まれのコシヒカリが今や東北各地で作られている。また、山形特産のさくらんぼが北海道でも実を結んでいる時代である。これからは温暖化への対応が課題となっていくが、気象ステージの変動は単純でない。想定を超える激しさで迫ってくるもの(豪雪、厳寒、低温、長雨、猛暑、干ばつ、超大型台風の到来、大洪水など)にどう向かっていくかが課題である。
押し寄せる社会変動の荒波
気象の異変に加え、社会形態の荒波も音を立てて襲いかかって来ている。食料危機が予見されているにも関わらず、自由貿易至上主義のTPPを強引に進めるやり方は、日本の農業と地域社会を崩壊に導こうとしているように思えてならない。
政府は「攻めの農業」や「農業の成長産業化」を掲げて衰退する地方の再生を図ると言っている。そのためには小規模農地の集積をはかり、大規模な経営体を作り上げるという青写真で、これが具体的な政策として地方自治体におりてきている。その骨格を成すのが「農地集積バンク」。これは伝統的な農業を一掃して大きな経営体に日本の農業生産の8割を任せるというもの。これが「攻めの農業」の青写真だが、私はこれを国主導の囲い込み(エンクロージャー)と受けとめている。
農業の持続的発展と多面的機能を明示した「食料・農業・農村基本法」の精神は今でも受け継がれていなければならないのだが、これがどこかに飛んでしまい、経済価値を生む産業に変更する政策が行われようとしているのが実態である。これまで地域を耕して列島の国土を守ってきた圧倒的多数の家族農業を切り捨て、誰のための農業をやろうとしているのか、私には到底理解できない。
加えて、最近急浮上してきたのが、中小農家の自立と相互扶助の組織体である農協を解体させようという過激な発想である。この発想がどこから出てくるのか不思議でならない。また、この国の地殻変動は食と農の分野にとどまらず、原発の再稼働、特定秘密保護法の強行採決、教育委員会制度の改編、集団的自衛権の行使容認などにも及び、戦後70年近く積み上げてきた日本のあり方を終わりにしようとする事態が相次いでいる。首相は「日本を取り戻す」と言うが、私はそれがどういう日本なのか、到底わからない。
足元の地域社会においては、急激な人口減少と高齢化が進み、耕作放棄地が増えている。また、各地の街並みが活気を失っている。専門商店は、全国チェーンの大型店やコンビニ店に客を奪われ、閉店を余儀なくされている。政府は「地方創生」という謳い文句で、新たな地域づくりをすると言っている。しかし、片方で構造的に農村と地域社会が崩壊することを進めながら、一方で地方再生を謳うのは決定的な矛盾ではないかと思えてならない。
われわれは地域資源を食い物にする資本の餌食になってはいけない、この状況を見過ごしてはいけない。今こそスクラムを組んで協働の力を発揮すべきときではないか。
3.11後をどう生きるか
先頃、福島県で「よみがえれ福島~有機農業のつどい~」が行われた。菅野さんたちが中心となり、有機農業の4、5団体が力を合わせて、福島の現場に立脚したかたちで今後の新たな方向を模索していこうということを、素晴らしいと感じる。農民、市民、学者、研究者の協働によって放射能汚染を克服する調査と実践活動を積み上げてこられたこと、これによって現代社会に新たな光が見えてきたことについては、感動を持って受け止めている。福島を起点として地域再生と創造の道が見えてきたのではないかと思えてならない。
中島先生が「自給的小農の意義と豊かさ」を強調され、過激な産業化がどれだけ人間社会に深刻な歪みをもたらしているかを論述しているが、これは傾聴に値する内容である。
国はひたすら産業化、経済成長の道をひた走っている。グローバル化と新自由主義の激流が日本列島を襲い始めていることをわれわれは受け止めなければいけない。ではどのようにしてこの流れに立ち向かっていけばいいのか。これについてはブックレットの中でキーパーソンとなる方々がそれぞれ書いている。私はこうした住民自治の力が突破口であり、新しい道を切り開くと期待を寄せている。
置賜自給圏構想
山形県で「置賜自給圏構想」が立ち上がり7月には法人化を前提とした推進機構という実践団体になっている。これは、新自由主義の激流の中で衰退し、消滅しかねない集落や地域、そして激しく過疎の進んでいく流れを住民自らが断ち切り、変換しなければならないという思いをもとに動き出した構想である。危機の時代に立ち向かう住民自治のひとつの動きといえる。
国が「攻めの農業」を振りかざして過激な政策を進めようとするなら、地域の中で「守る農業」を基本テーゼとしてとして立ち向かっていくという考え方である。自給圏においては、食と農とエネルギーの自給を基軸にして地域づくりを考える。上杉鷹山が成し遂げた改革に学びながら、「身土不二」を具現化していく。これは地域内でとれるものの大半を食材として食卓を作っていけば健康で長生きできるという教えである。地域社会のすべての領域において、命と環境を優先するものの考え方によって再建し、新たな道を切り開いていくということ。それを産学官、福祉、医療の結合によって実現しようとしている。地域の組長に賛同いただき、国会議員からも党派を越えて積極的な支援のエールを送っていただいている。これから新たな道筋が生まれてくることに強く期待している。
自給圏というと閉鎖的な社会というイメージを持つかもしれないが、決してそうではなく、開かれたローカリズムを念頭に置きながら進めていく。先日、自給圏構想を考える会の集会には300名ほどが集まった。山形大学人文学部長の北川先生はフランスの事例を提示し、自給圏構想の可能性を示した。これは、ブルターニュ地方で1970年代から始まった「フランス郷土圏」という興味深い取り組みで、地方自治体やコミュニティとはやや異なる性質を持つ。2008年の時点で381ほどの郷土圏が動き出し、地域の自律に向けて活動を展開しているということである。これは置賜と重なる部分が多い。置賜自給圏は、構想にとどまらず推進機構としてスタートを切り、自律の処方箋として注目されている。
たかはた共生プロジェクト
原発事故後、風評被害が深刻であったことから「たかはた共生プロジェクト」が始まった。データを示しても認めてもらえず、有機農業研究会以来40年の歴史を積んできた有機農家も大変な苦難に直面していた。その頃、交流のあった早稲田環境塾の方々が、高畠の有機農業をなんとかして救おうと手をさしのべ、「青鬼クラブ」をつくった。これは個人の加盟で直接生産者から消費者に食べ物を届けることを目指して、試験的に行なわれたものである。開始後、取り組みがすぐに広がったわけではないが、1年くらいが経過し、ネットワークができてきた。これは新たな提携関係である。
しかしながら、たかはた共生塾はこれをひとつの基軸とはするが、より幅広く都市と農村の垣根を越えて、双方向で新しい時代の人間の生き方を創り出していこうという取り組みである。つまり、価値観を共有している人と人との結びつきによって、新たな生命共同体を作り上げるというもの。2年間の準備期間を経て、今年4月に「共生プロジェクト」を正式に立ち上げた。都市と農村の垣根を越えて人を結んでいくのが基本である。毎月第3木曜日には、毎日新聞本社1階のモッタイナイステーションで「青鬼サロン」を開催している。そこでは、その月のテーマに基づいた文化講座を行い、地場産品の即売もおこなっている。この最大の特徴は、生産者と消費者に加え、メディアが関わり、市民・農民・メディアの3結合によって、動いていることを即情報として発信してもらえる場であるということである。
CSOネットワークと有参協が示すモデル
ブックレットではそれぞれの地域づくりのキーパーソンが自ら語っており、まさに新たな地域づくりのモデルケースと受け止めている。有機農業参入促進協議会が出している冊子にもモデルが含まれているが、これとブックレットのモデルは重なるところがある。これらを組み合わせると、日本の先端的な地域づくりの実践事例がしっかり刻まれているといえる。これを自分たちの地域でどのように活かすことができるかを考えると、新たなヒントを見出すことができるであろう。また、事例の中には必ず汗を流して情熱を持って取り組んでいるキーパーソンの存在がある。
今、国が協同組合を解体させようとしているからこそ、協同組合の旗を掲げて有機農業は新たな取り組みを進めていくべきではないか。既存の農協の中に、例えば有機農業協同組合を作ろうと思えば、専門農協としてつくることができる。生産者が主体となって全国にネットワークを組みながら、新たな時代を農の現場から切り開いていくことが必要。
生協の中には、農協や生産者が生み出したものをただ受け止めて消費者に届けるという流通にとどまらず、生協も一緒になって農業生産の場で汗を流さなければならないと考えているところもある。協同組合は構成員の幸福の増進を果たすということにとどまらず、公正な社会の実現を目指さなければならない。必ず工業化社会が行き詰まり、人々が農山漁村に還流する時代が来る。その日のために今から受け皿を整えなければならない。
グローバリズムの対抗文化
これからグローバリズムの対抗文化を築いていかなければならない、ということを考えていきたい。これはブックレットが示している地域の内発的発展に行きつく。外からの開発に頼らず、地域の力で、地域住民の主権のもとで新しいものを作り上げていかなければならないのではないか。そのためには農の世界が持っている資源、地域の宝を発掘し、磨きをかけることが重要である。
これは、歴史に学ぶという意味合いも持っている。歴史に学ばずに未来を洞察することはできない。また、これは地域住民の力だけでは達成できないもの。災害に打ちのめされた地域は、都市の市民と連帯を築きながら復興の力を生み出していかなければならないと考える。つまり、都市市民と共に輝く農の時代を手繰り寄せていくということ。
昨年(2013年)は「国際協同組合年」であった。今年は「国際家族農業年」、そして来年は「国際土壌年」である。土の力にようやく世界の人が目覚めてきた。健康な生き方を実現するためには、健康な土から生命感あふれるものを日常的に体に取り込んでいくことが大事である。菅野さんたちの実践によって、放射能に打ち勝つ土の力が示されている。来年は生きている土の力の大きな要素、大きな力(現代の危機を乗り越える、汚染さえものり越える力)を発信してほしい。菅野さんたちはトルコで開かれるIFOAM(国際有機農業運動連盟)の世界大会に行かれると聞いているが、福島の壮絶な体験をしっかりと示していただくことが世界中の人に勇気を与え、これからの生き方を示す上で計り知れないものがあると思う。
脱成長の新たな思想を汲む
 残念ながら日本では今、人類史の潮流に逆行するかたちで国策が進められようとしている。このままでいいのかという思いがある。そのような大局を変えていくのは、やはり草の根の力だと思う。農が持っている根源的平和主義、命と環境を何よりも大事にする有機農業、そして心ある市民の方が一緒になり時代に後戻りする動きに異議申し立てをしていくことが重要である。
残念ながら日本では今、人類史の潮流に逆行するかたちで国策が進められようとしている。このままでいいのかという思いがある。そのような大局を変えていくのは、やはり草の根の力だと思う。農が持っている根源的平和主義、命と環境を何よりも大事にする有機農業、そして心ある市民の方が一緒になり時代に後戻りする動きに異議申し立てをしていくことが重要である。
西欧社会では脱成長のという思想的流れがある。わが国が経済成長一辺倒になっているときに、世界では脱成長の中で成熟社会、新たな文明を創造していこうとする動きが出ている。まさに生命文明のパラダイム転換といえる。ここでは、人々が贈与、幸福、自律の道を選択するようになる。等身大の簡素な生き方で十分に持続していくという倫理性を、脱成長の哲学は持っている。それはアジアの伝統文化にも息づいているものだと思う。
若い世代に希望の萌芽
最後に、私たちに希望を持たせるのは、若い世代の農村回帰へのうねりである。「自治体消滅論」が掲げられている一方で、若い世代が農村に回帰し、確かな歩みを進めている。わが町にも若い就農者が次々と誕生しており、志望者もいる。多くは有機農業の子弟である。親の世代が有機農業を40年続けてきて、これからというときに子どもや孫の世代が継いでくれるというのは大きな希望である。そのような若い世代の新たな萌芽に大きな希望を託して話を終わりたい。
<第二部 報告とパネルディスカッション>
【報告】
菅野正寿 有機農家/福島県有機農業ネットワーク理事長
「原発事故から見えてきた農の価値と地域の力」
 私からは、原発から3年経った福島の現状をお話ししながら、皆さんと3.11後の新しい農と市民のあり方を考えていきたい。私は35年前の学生時代星先生のところで住み込みで働かせてもらった。大恩師である星先生と同じ場に立てて光栄。私の活動の基本は高畠であり、これからの地域のあり方、農業のあり方について常に星先生に示唆をいただいてきた。高畠を理想として、このような故郷をつくろうと頑張ってきた。その中で原発事故が起きた。
私からは、原発から3年経った福島の現状をお話ししながら、皆さんと3.11後の新しい農と市民のあり方を考えていきたい。私は35年前の学生時代星先生のところで住み込みで働かせてもらった。大恩師である星先生と同じ場に立てて光栄。私の活動の基本は高畠であり、これからの地域のあり方、農業のあり方について常に星先生に示唆をいただいてきた。高畠を理想として、このような故郷をつくろうと頑張ってきた。その中で原発事故が起きた。
震災から3年半経つが、「除染」、「損害賠償」、「復興」、という3つの言葉が新聞から消えた日はない。中間貯蔵施設の問題などが毎日取り上げられ、収束どころではないというのが福島の現実である。未だに13万人(都内に6,000)人が避難しているのは異常な状態だと思っている。
今日の新聞では、災害関連死が1,753人とある。津波で亡くなった1,600人よりも避難して亡くなった人のほうが多い。これは岩手、宮城よりも福島が異常な状態だということ。さらに自殺者が56人もいる。川俣町山木屋地区(二本松市から20分のところ)では、7月に渡辺さんが焼身自殺した。夫の幹夫さんが東電に自殺と原発事故との因果関係を認めるよう損害賠償を訴え全面勝利した。これには大きな意味がある。つまり、裁判の中で企業の社会的責任を認めるようにと問われている状況である。二本松市でも震災の年の12月23日にりんご畑の木の下で自殺があった。そのような状況が続いているのが現実である。
今二本松市では、浪江町の方3,000人が仮設や借り上げ住宅に入っている。損害賠償が進まず、帰りたくても帰れない、復興住宅も進んでいないという状況である。これが3年半つづくのは大変な状況。飯舘村も同じような状況で酪農家も自殺をしている。これについての裁判も始まっている
これまで除染の目安は、毎時0.23マイクロシーベルトであったが、つい最近、国は個人の被ばく線量を重視して対応していく方針に転換した。これは国がこれ以上予算を出さず、市町村任せにしているかたちであり、この流れが心配である。福島有機農業ネットワークでは今年の春から有機農家25人の被ばくを24時間調査している。自宅の中では0.2以下だが、畑や田んぼに行くと、0.4~0.6となる。特に若い農業者の健康管理や実態調査を早急にやってほしい。そのためにまず自ら調査を進めている。
もう一つ、中間貯蔵施設について。福島県と国が大熊町と双葉町に中間貯蔵施設の工事を出した。しかしこれは押し付け以外の何ものでもない。本来は問題を起こしてきた電力会社が責任を持ってやるべきこと。それを押し付けるということに、地元の町民は納得していない。電力会社の責任が見えなくなってきて、だんだん市町村に任せるようになっている。これでは敵が町長や市長になり、地域が分断されていく。
さらに、昨年の秋のがれき撤去のときに放射性物質が飛散していたことがわかった。飛散した放射性物質が南相馬の稲で見つかったのだ。有機農家は去年・一昨年と20ベクレルだったものが、100を超えたことにがっかりした。これは上から落ちてきたとしか考えられなかった。このことを国が認めたのは今年7月のこと。国と東電は半年以上も情報を隠していた。国や東電の体質は3年前と変わっておらず、きっちり住民に情報を公開していない。このような状況では、これから廃炉に向けた30、40年の間にまたそういうことが起きるのではと不安になる。このような現実が突きつけられている中、私たちは声をあげていかなければならない。
今日は森林調査を一緒にやっていただいている横浜国立大学の金子先生がおいでになっている。震災後の5月に新潟大学、茨城大学、東京農業大学、横浜国立大学の有機農業学会の先生方にはいち早く二本松・東和にお出でいただき農家と一緒に実態調査をしていただいた。本来、田んぼ、畑、山、川の実態調査は、農林水産省が農業や農民の健康を守る立場ですべきことだが、3年経っても一向に行われていない。これは大問題である。チェルノブイリでは国が責任を持って一枚ごとの田んぼの調査を今でも継続している。
新潟大学の野中先生、横浜国大の金子先生には何百回も足を運んでいただいて、農家と研究者による実態調査を進めてきた。これによって見えない放射能の見える化に取り組むことができた。これは大きな成果だと思っている。特に肥沃な、有機的な土壌ほどセシウムが土に固定化されて稲や野菜には移行しないということが検証されてきた。耕さないところは今でも移行するということなので、耕すことによってセシウムが土中に深く吸着されるということが見えてきた。
日本は稲作文化、農耕文化でその土地を耕し続けてきた。土着をして草やわらなど有機質を入れて土を耕してきた。チェルノブイリとは違う、日本の土壌が生んだ土の力がある。この放射能に対する大きな力が今回発揮されたのだと思う。これを野中先生らが検証して、今、そして今後も対策を進めようということで取り組んでいる。
しかし、残念ながら山の汚染は深刻。3年前の落ち葉が腐ってカビが生える。このカビ菌がカリウムと一緒にセシウムを吸ってしまいワラビ、ゼンマイ、タケノコなどからまだ高い放射能が検出される状況。二本松市はタケノコとゼンマイがまだ出荷制限の状態。木が落ち葉から吸ってまた葉が落ちるという循環型でセシウムがいつまでたっても山から抜けない。この山の汚染は深刻である。このように山林除染がほとんど手つかずというのが福島県の実態であり、対策を早急にやらなければならない。そのために今金子先生らとともに森林除染の実証を東和地区で始めている。
昨年、水俣を訪れた。嬉しかったのは、専業の漁師50人、兼業の漁師200人が今魚を捕ることができていること。農業、漁業を辞めるということはそこで技が途絶えてしまうということ。水俣でも若い漁師さんたちが頑張っているということで私たち福島の農家も励まされている。先ほど星さんから「地方創生」の話があったが、水俣も原発も米軍基地もすべて地方に押し付けている状況の中で、この問題を解決せずに「地方創生」などというのはとんでもない。本当に「地方創生」というなら、農林漁業をしっかり守る、原発をなくす、基地をなくすなど、これが本当に地方に向き合った新しい創生ではないかと思う。「福島の再生なくして日本の再生なし」と言っておきながらなぜ東京オリンピックをやるのか?それが福島の声である。
米の全袋検査が今年も始まった。12月いっぱい福島に来れば検査場を見ることができる。2011年の秋から土やもみがら、玄米を測ってきた。その中で、たとえ土壌が2,000、3,000ベクレルで汚染されていても玄米には移行しなかった。わらやもみがらには20~50ベクレルくらい出ているが、玄米には出なかった。この経験から種の持つ力、植物が子孫を残す力はすごいものであると思った。だからこそ日本の稲作が3500年も続いてきたのだと思う。まさに化学的なものより農民的な技術のほうが放射能についても大きな力を発揮したということであろう。
ブックレットでも触れているが、二本松市の神社のわきに石碑があり、230年前の天明の大飢饉の惨状を刻んでいる。旧東和村、旧山木谷村で多くの人が餓死し、3年後に石碑が立てられた。この教訓から農村復興策として、特産品(養蚕、葉タバコ)や酪農、綿羊、大豆、小麦、じゃがいも、雑穀を奨励して開墾と食糧増産が図られてきた。今の多様な暮らしは過去に様々な災害に見舞われたからこそ生まれてきた日本型の食生活だと改めて感じる。かつて農村復興策として官民挙げて農林漁業を守ってきた。だからこそすばらしい日本の土と豊かな食生活が育まれてきた。そのことを考えると今回の原発事故を受けて、改めて本来の農林漁業の役割をしっかりと都市の市民の皆さんと共有していくことが大事だと思っている。
今年から有機ネットでは「耕せ!ふくしまプロジェクト」を始めた。これは市民や企業が皆で一緒に耕しましょうというもの。米や味噌を自給する、そういう時代が必ず来ると思っている。
今年、博報堂やヤフーの方に来ていただき、私のところでは大豆、会津では酒米を創るプロジェクトをスタートした。有機栽培で小麦も大豆もつくり、それを醤油、味噌、納豆と、様々なものを自給していくプロジェクトをしていきたい。都市と農村が食料や防災で良い関係を築いていく、まさに共生の時代がきたのではないかと思う。そのために都市の住民の皆さんと一緒に取り組みを進めていきたい。
昨年インドのヴァンダナ・シヴァさんにお会いしたときの「単一の社会は支配をつくり、多様な社会は共生をつくる」という言葉が印象に残っている。農家、市民、企業が共に新しい時代をつくっていくことが大事ではないか。今年、(南アフリカの)マンデラ政権時代に閣僚だった方が田植えに来た。マンデラ氏は「虹の共同体」ということを言った。3.11は多様な社会の重要性を教えたと思う。これからも地域の中で、実践を続けていきたいと思っている。
古沢広祐 國學院大學経済学部教授/共存学プロジェクト
「生物多様性の危機と有機農業・家族農業の可能性」~国際有機農業運動連盟(IFOAM)世界大会に向けて~
地球温暖化対策の切り札として原子力エネルギーが叫ばれ、「原子力ルネッサンス」として動き出したときに福島の原発事故が起こった。事故のレベルは、チェルノブイリと同じレベル7だが、当初はレベル4とされ、当事者さえ事故の深刻さを把握できていなかった。レベル5の事故は世界各地で起きている。現在世界では400以上が稼働しているが、2030年には世界で800基、今の2倍になると原子力業界は予測しており、世界全体が原発惑星化するという状態が進みつつある。
地球の生物の歴史の中で5回絶滅の時代があったが、今は最大規模の事態が起きているといえる。そのような状況で、1992年に開催された地球サミットにおいて2つの重要な条約が成立した、気候変動枠組み条約と生物多様性条約である。気候変動枠組条約については、年末にCOP20がペルーで開催される。しかし対応は遅れており、気候変動を防ごうという予防の段階はもはや諦め、どう適応するかというレベルになっている。つまり、自然災害の頻発を前にして、その損害に対してどう対応するかということが議論されだしている。
生物多様性に関しては、これまでのモノカルチャー的な文明に対して、今まで隠れていた価値をもう一度見直していこう、認識していこうという動きがある。そして家族農業、地域が伝統的に持っている可能性、潜在的な力、こういうものの意義と新たな可能性を再評価する視点が生物多様性条約の中には含まれている。しかし、現実に起きているのはモノカルチャー型の拡大であり、それをどのように共生型にかえていくかのせめぎ合いが続いている。
では、普段の生活をどう変えていくか。食の世界こそが今の私たちを支えている基盤である。食の世界に何が起きているかを大きなスケールで分析した本として『フード・ウォーズ』がある。ファストフード対スローフードなど、どういう食のスタイルを受け入れるかによって、どういう世界が創られるかということにつながっていく。
生物多様性条約の締約国会議ではいろいろな問題が議論されている。これは自然との共生を目指す条約だが、バイオテクノロジー、ジオエンジニアリングなどの問題についても、環境条約の中では生態系への脅威問題ということで議論が進んでいる。生物多様性条約の大きな論点として、単なる保全というより、それを支える家族農業、小農業、地域の伝統的な文化を含めての地域の文化的多様性と生物の多様性がつながっているということがある。特に重要なのが自然と人間の間をつないでいる里山などの半自然。その中核部分に農林水産業などの一次産業がある。そういうものへの再認識という意味で、国連は2014年を「国際家族農業年」と定めた。もうひとつ、人類の歴史的生産活動の文化遺産として農業が基本にあるということでFAO(国連食糧農業機関)が定めた「世界重要農業遺産システム」がある。世界30数か所、日本では5つある。これは、地域の中で人間が生きてきた足跡を農業遺産というかたちで認識し直そうということで、農業の持っている可能性が改めて見直されている。
従来は一次産業が基盤だったが、近代化の中で第二次、第三次と逆転の現象が起こっている。もう一度生態系の持っている恵みを踏まえた社会をつくっていくことが重要であり、それは農業、広く言えば第一次産業の復権の時代ということを意味している。私たちは未来をどう描くのか。「グローバル化の進展」か「ローカル化の進展」か、「自然共生型の社会」か「自然改変志向の社会」か、という4つのシナリオがあり、大きな岐路に立っている。その中で私たちは自然共生社会への道筋をどう見出していくかが課題である。
浜口真理子氏 CSOピースシード代表/人々とたねの未来フォーラム事務局
「タネを通して食と農、地域と世界をつなぐ」
~生物多様性:COP10からCOP12へ(日本・インド・韓国)~
20年前、福岡正信さんから種子戦争の話を聞いたのが種子に関わるようになったきっかけである。子どものころからタネが好きでタネと遊べる環境にいた。有機農業、食の安全という方面というよりも、飢餓やコミュニティー構築など開発からのアプローチだ。タネと向き合うことは、条約や民俗等社会で起こっていることほとんど全てに向き合うこと。死ぬまで勉強し続ける必要があると感じている。
地域と世界を結んでいこうということでお話をする。3.11後の農業についての発表のために、リオ+20に参加した。成田の近くに住んでいて、放射能の影響も受けた。有機農業内に価値観の違いが見えた。有機により付加価値をつけ売るための有機農業をおこなっている人たちと、成田闘争の伝統の中で、「いのち」を大切に農業をおこなっている人たちがいる。
ブラジルでの種子交換会で知り合った人に、シードバンクを設立した人がいた。種子を探し守る活動をおこなっていたが、貯蔵庫を見せてくれる際に、開口一番「GMがない」ことを自慢をした。ショックだった。また、ブラジルのオーガニックは海外に売っていくためのもので、アグロエコロジーには社会正義、公正、公平などが含まれるという違いについて説明を受けた。
COP11でインドに行った。名古屋議定書を良いものと信じていたが、議定書により、生命が金勘定の枠組みの中に入れられてしまった悲しさを訴える人たちもいた。名古屋議定書の中では、本当に大切な魂は薄まっていると感じるようになった。栽培植物の長い歴史の中で、今の作物があることが出来れば、争いも無くなる可能性があると思う。生命倫理は大切なテーマであり、国際社会で話し合うべきだがまだなされていない。
インドの大学生と対話をした。遺伝子工学を学んでいるが卒業後は農村に入るという。GMを学んでいるからこそ、GMではなく在来品種の大切さを伝えたい、と語った。すでに問題で苦しんでいるからこそ、兵法も違うことを目の当たりにした。
Peoples Biodiversity Festivalsで種子の関係者に出会った。アクティビストと現場の実践者の間にはギャップがある。アクティビストは「生命にパテントはいらない」というスローガンを掲げていたが、一方、時間をかけて品種改良をおこなっている農民は、品種認証されることは嬉しく、客観的に認められるということをご褒美と感じていた。長年育ててきた種子を人に分けた後はその種子がどう育つのかを知りたいもの。アクティビストはそのような農民をリスペクトはするが、マニフェストづくりには強い言葉が使用された。
種子ブームの中で、種子がものとして独り歩きしていく。ここ2~3年、そのような形に違和感があるとの声が出てきている。国際社会のコンテクストの中では、情緒的なものは受け入れられないが、日本には情緒的なタネへの思いがある。日本ならではの仕組みが必要なのではないかと感じている。
守り手が高齢化し、また守るのが大変だということで、近年はイネの多様性を守るプロジェクトにも力を入れている。多種多様な品種があるが、昨年は350品種、今年は55品種を育てている。成田空港から20分くらいの所で、見学を受け入れているので、稲の多様性の美しさをぜひ見に来てほしい。
【パネルディスカッション】
モデレーター:大江正章(コモンズ代表/アジア太平洋資料センター共同代表/「地域の力フォーラム」委員長)
大江:主に3つのテーマ、①福島に関わること、②家族農業について、③農山村と都市の新しい結びつき、という点に絞って議論を進めていきたい。また、先ほど菅野さんが山林の汚染に言及されたが、この問題に関して私たちが知っている中で一番先駆的な研究をされている横浜国立大学の金子先生がいらしているので、取り組みについてお話しいただきたい。
金子氏:東和の森林を伐採して木材チップをつくった。そうすると7~10%くらいの放射性セシウムを、そこに勝手に入ってきたカビが吸収する。それを山から降ろすことが除染になるので東和の方と一緒にやっている。放射線の専門家ではないが、事故の後、土壌に放射性セシウムが集まると(研究の対象としている)生き物が汚染されると知って始めた。事故で感じたのは、放射能汚染で何が起こるかについて研究者は良くわかっているものの、意外に発言しないということ。私としては何が起こるかの予想がついていたので、農家と共同で作業を進めている。
 大江:震災直後から南相馬の支援を積極的にしてこられた佐久総合病院の色平さんが会場にいらしているのでメッセージをいただきたい。
大江:震災直後から南相馬の支援を積極的にしてこられた佐久総合病院の色平さんが会場にいらしているのでメッセージをいただきたい。
色平氏:市長の桜井さんが十数年来の友人であったので、直後から現地に入っている。今日は星さんの話が聞けて光栄。「危機の時代に立ち向かう住民自治」、「開かれたローカリズム」、「グローバリズムに対抗する脱成長」、「簡素な生き方」というのは、佐久総合病院がこの70年間地域で追及してきたことそのもの。私は、若い人(医学生や看護学生)が地域のお年寄りを訪ねて、農作業・機織り・炭焼きなど農的な体験をする、ということをやっており15年間で2,000人ほどが参加した。
大江:ご存知の方もいると思うが、佐久総合病院は農村の地域医療で最も先駆的な医療をし続けている。次に、福島県東和地区には3.11以降に新規就農者が複数訪れているが、その新規就農者がどのような状況になっているか、地域に与えた意味などを菅野さんにお聞きしたい。
菅野:3.11以降、東和に30代から40代の7名が農業を志してきた。彼らは、3.11があったにも関わらず東京の人に変化がないことがおかしいという思いを持っている。体験ツアーに来る人も、社会が何かおかしいと思っている。その流れは一過性ではないと感じる。若い世代は高度経済成長の中で育っているが、働き方や暮らし方に疑問を持ち、口にしている。その中で行きつく先が農業だということではないか。
大江:新規就農者をサポートするシステムについて伺いたい。
菅野:強みは地域のNPO(住民主体の組織)があったこと。行政は手が回らず、農協も組織を守るのが精一杯である。そのような状況で、既存の組織ではなく住民主体の組織があるかどうかが大きく問われている。東和ではNPOが新規就農者の窓口となり、相談を受け、土地・空き家・堆肥・販路等の斡旋をおこなっている。そういうものがあるかないかで地域からのサポートは異なってくると思う。
大江:「ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会」は自分たちの地域を自分たちの手で守るという意味で、農業者を中心に地元の商業者や自治体職員も加わって作られたNPO。道の駅で年間2億の売上がある元気な組織。東和では新規就農者をまったくの初心者から支援している。また、「あぶくま農と暮らし塾」という私塾もできた。ここでは中島先生を中心に農業技術、文化、食から社会活動など全面的なサポートをしている。この地域は日本でも稀有な地域である。それが東和に3.11後も人が来て定着している要因であると思う。現在までに全体で40人くらい来ている。次にIFOAM世界大会の話をしていただきたい。
菅野:3年に1回、IFOAM世界大会があり、今年イスタンブールで開催される。IFOAMジャパンから、福島からのメッセージを発信してほしいと声がかかり、10月13日から一週間の日程で参加する予定。参加するのは福島大学の先生と20代の青年、私の3名。トルコは地震国だが、日本政府は原発の技術を提供しようとしている。また、チェルノブイリのときにトルコ政府は一切調査をしなかったという経緯がある。そのような国で福島の状況を伝えて思いを同じくしたい。
大江:古沢さんの発表に「家族農業が生物多様性を守る」という話があったが、その意味は?
古沢:どういうものを食べるかによって世界が変わるということ。例えば、作物や家畜の品種の多様性でいうと、巨大食品産業が提供するものの場合、主食になるようなものは数十種類に限られてしまう。それが各地の地域の伝統的農業を担う小農家が供給する食生活では、数千から数万の多様な品種が存在している。日常的に食べるモノを通して、モノカルチャーの世界に中で生きていくのか、生物多様性とつながるような様々な種の多様性の世界につながっていくのか、大きく変わってしまうという意味で話した。
大江:有機ネットの中で、自家採取はおこなっているのか。
菅野:種取りには取り組んでいないのが現状。伝統野菜の種を守ろうということはあるが、なかなか自分でやろうというところまではいかない。同じ地域でも気候が異なるので、それを守っていかなければいけない。認識はあるが、実際の農業の中でどうしていくかということだと思う。
大江:浜口さんから何かメッセージをいただきたい。
浜口:政府がいう「伝統品種」と、「地域の品種」は概念を分けなければいけない。伝統品種はブランド化されたもので、一度絶えてもジーンバンクから持ち出して再生していけば作ることができる。地域の品種は、脈々と自給をベースに進化してきた。そこは区別したい。2009年に聞いた話だが、ヨーロッパでは家庭菜園が作物の多様性を保つための重要なファクターだということが研究の対象になっている。これから日本でもそうなるといいと思う。
大江:いわゆる伝統品種がある種ブランド化されていることには警鐘を鳴らさなければならない。最後に「農山村と都市の結びつきを考える」ということについて、こんなことをやっているというのがあれば。
菅野:震災後、長女が「きぼうのたねカンパニー」という会社を立ち上げた。HISと提携して、野菜の種まき、田植え体験ツアーなどを毎月のように行い、毎回バスが満席となっている。20代・30代が多く7~8割が女性。体験を通して農業の価値を感じ取ってもらっている。これを入口として、体験から定住への流れをしっかりつくるときではないかと思っている。
大江:他にご意見感想を。
古沢:消滅する地方自治体というレポートが出されたが、ヨーロッパでは、一極集中とは逆方向、地方の中の様ざまな拠点に若い人が戻り始めているという流れがある。その視点で見ると、農山村や地方都市が縮小し消滅していくという日本のレポートは一面的でおかしい。全体を見るとそう見えるかもしれないが、ミクロに見ると若い人が地域の中に入り込んでいろいろな活動展開をしている様子が見え出している。見方を変えると、そのような可能性が小さな火のように燃え上っている。現実世界を統計的に見て、乱暴に切り捨てていくのではなく、実際にきめ細かく見ていくと新しい可能性、希望の光が見えてくる。
大江:最後に星さんからひと言。
星:農村には展望がないという前提に立っている増田レポートは、移住するようにというようなもの。道州制の枠組みの呼び水として問題提起をしたという感じがする。しかしそれは必ずしも妥当でない。それぞれの地域社会の実情は単純なものではなく、大地に根差した生活をしている。若者の農村回帰の流れはわれわれにとって希望である。そういった動きは今までのモノやカネを何よりも大事にする生き方にこれ以上ついていけないという、人間としての価値観に基づいているのではないか。IT社会の虚しさを感じ取り、自然と向き合って命を育んでいく農の豊かさに目覚めてきたのではないかと思う。
農業は非常に自在性のある営みである。管理社会の中のように上から指示されたり、押し付けられたりするものではなく、自律し、自分で考えて計画を立て、実践できる。そういう自在性が人間にとって重要であることに気付いたのではないか。農の営みは誰かに環境を創ってもらうのではなく、自分で仕事を創り出していくという人間の自律性につながる大事な営みである。
生き物の好きな人たちが、五感で、感性でとらえて自分を投げ込もうとしている。生き物が好きだということは命を何よりも大事にすることと直結している。わが国の若者たちは一番大事なところに目覚めてきた。生きた土をつくってきたが後継ぎがいないと途絶えてしまうという虚しさがある。私の場合は、一世代飛び越して孫に引き継いでもらえるということが大変な希望である。個人的なことだけではなく、日本の地域社会そのものに対して希望になると思う。農村回帰の流れを育成、助長する環境を地域の中に、それぞれの条件や個性に合わせて作りだしていくという大変大事な時代を迎えていると私は思っている。
大江:80年代後半から90年代に「たかはた病」というものがあった。星さんたちが中心となっている農学校に数日間行った人が、たかはたが大好きになって移住するという社会現象。これが最近は聞かれなくなった。なぜなら、高畠だけではなく、全国の農山村でいろいろな取り組みが見られるようになったから。そういったところの大半は小さな農業であり、有機農業を大事にしながら地域をつくっているところ。今、島根県や鳥取県の人口数千人規模の農山村で、転出より転入が多いという市町村がこの3,4年間に8つほど生まれている。ほとんどが山村と島。この動きは今の若者たちの志向を反映している。
増田レポートは2010年の国勢調査に基づいたものであって、3.11以降の動きは反映されていない。われわれは実証に基づいてこのレポートを批判、そして乗り越えつつこれからの新しい農山村と都市のあり方を考えていきたい。そのときの重要なキーワードは星さんのレジュメに書かれていた「守る農業」ではないか。国は「攻めの農業」と言っているが、地域社会を守る、環境を守る、農を守る、種を守る、そのことが新しい地域社会を切り開いて行くことにつながり、本当の意味での「強い、持続可能な農と地域社会」になるのではないかと感じている。菅野さんが「体験から定住へ」とおっしゃったが、別な言い方をすれば「交流から移住へ」と言ってもいいだろう。こうした流れはかなり広くなりつつある。みなさんがそれぞれの地域や立場でそうした流れを一層押し上げていくことをしていけば、新しい日本の姿が浮かび上がってくるのではないか。