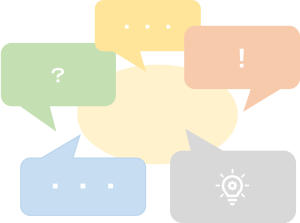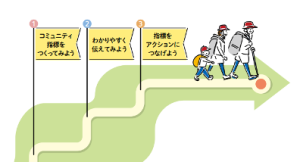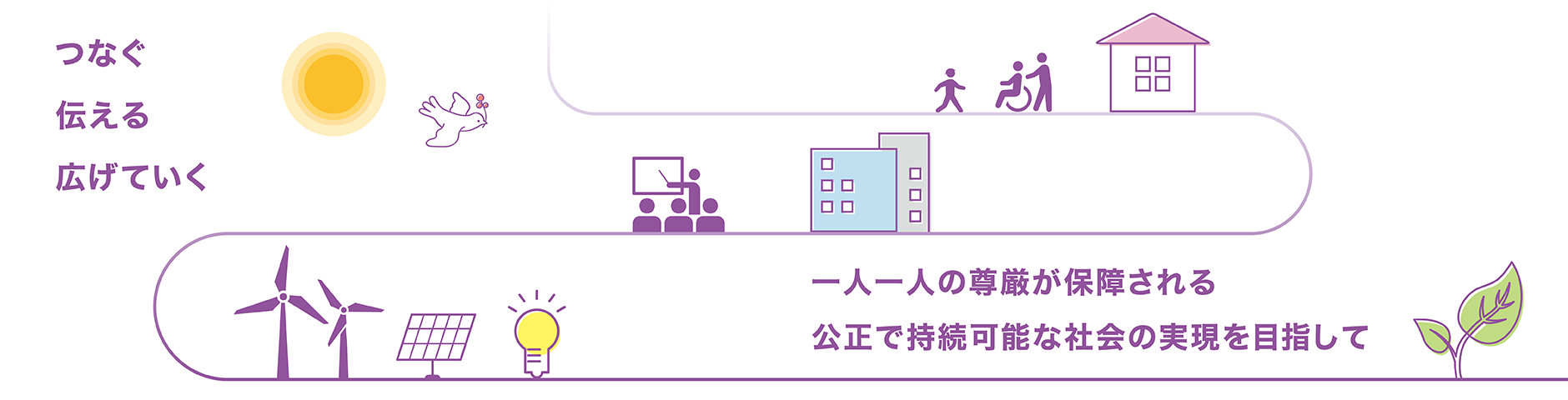CSOネットワーク(CSONJ)を取り巻く人たちをご紹介するインタビューシリーズ「CSONJな人たち」第5弾は、常務理事 今田克司(前編)です。一回では紹介し尽くせないインタビューとなったため、前後編の2回に渡ってお届けします。前編となる今回は、現在にいたるまでの、今田さんとCSOネットワークの歩みについてです。

――今田さんがCSOネットワークの前身であるCSO連絡会に関わるようになったきっかけを教えてください。
わたしは90年代はほぼサンフランシスコベイエリアにいて、CSO連絡会が誕生した99年当時もアメリカで活動をしていました。
当時のアメリカのNPO活動は日本よりも進んでいると言われていて、日本からの視察の受け入れなどを行なっていました。これには、日本で80年代後半から90年代、NPOや市民セクターを「職業」として成立させたいという声があったことが背景にあります。阪神淡路大震災が起きた95年がボランティア元年と言われますが、98年にはNPO法が誕生し、この動きを加速させました。プロフェッショナルとしてのNPOが求められるようになってきました。アメリカで訪問視察団の受け入れや通訳に携わるうちに、アメリカのNPOを日本に紹介するような役割を担うようになっていきました。97年には自分でNPOを立ち上げ、NPOのインターンシッププログラムを始め、この評判が日本に広がっていきました。
一方で、CSO連絡会は日米のNPO連携の枠組みを作る目的で始まったものです。日米の政府間の国際協力・協調の枠組みとして「日米コモンアジェンダ(地球的展望に立った協力のための共通課題)」があり、政府間、企業間の協議に加えて市民社会(CSO:civil society organization)でもやろうということで、日本側の連絡母体として、CSO連絡会が誕生しました。99年でしたか、当時アメリカで活動していた私にもこの動きが伝わり、その後、2000年に日本に戻った際に、わたしがCSO連絡会の事務局長を務めることになりました。
――CSO連絡会からCSOネットワークに変わった経緯を教えていただけますか。
連絡協議会の役割が終了したのが直接のきっかけです。政権交代の影響でコモンアジェンダの枠組み終了し、アメリカのカウンターパートも活動を終了しました。そこで、2004年にCSO連絡会からCSOネットワークへと改名し、体制も変更しました。
――CSOネットワークへの組織変更で活動はどう変わったのでしょうか。
それまでの延長線上に、新たなフォーカスとして二つのことが育っていったと思います。

2013年11月、原発被害に遭った福島のりんご農家を視察する
ひとつには、市民の巻き込みです。市民が主体になって、実現したいことに労力やお金、時間を投入して解決するように仕向けていくということです。連絡会当時は「日米」協調の枠組みと言っていたものの、その目的は地球規模課題の解決でした。当時はSDGs(持続可能な開発目標)の前身であるMDGs(ミレニアム開発目標)に向けての活動が展開されており、MDGsを達成するための日米協調という位置付けでした。市民社会の横のつながりによるグローバルな視点から活動する中で、途上国の課題を語るには途上国側の市民のオーナーシップが大事であるという声がNGOの中で強くなっていました。
市民の巻き込みを具体的に行ったのが、「ほっとけない世界のまずしさ」キャンペーンです。これはもともと2005年にイギリスで開かれたG7サミットに合わせて、イギリスのNGOがPR業界と組んで始めたものでした。英語ではMake Poverty History(貧困を過去のものに)として展開されました。MDGsのゴール8「グローバルパートナーシップ」に貢献するもので、白いTシャツやリストバンドを身につけながら、貧困、債務、貿易の3つのテーマで政策やマクロな社会のあり方の変革を訴えました。このキャンペーンを日本で担ったのが、日本のNGOのコアリションで、CSOネットワークもその中核を担いました。CSOネットワークとしては、どうしたら地球規模の課題に興味がない人に気づいてもらえるかという問題意識があり、こうした活動が啓発のきっかけになると考えていました。地球規模課題解決のための市民の役割を考えるきっかけを提供する活動でした。
二つ目は、NPOにおける新たな、そして先進的な知見などを日本に紹介することです。成り立ちから分かる通り、CSOネットワークではアメリカや英語圏の情報が入って来る環境がありました。そうした情報を得る中で、NGOの社会における位置付けや組織や事業のあり方をアップグレードしていく必要性を国内に発信していく役割が育っていきました。
一例として、本の翻訳に携わったこともあります。2006年、マイケル・エドワーズ著『フューチャーポジティブ』(日本評論社)の翻訳をCSOネットワークは監修しました。
当時、NGOの役割は過渡期にあり色々な議論がありました。アメリカでは10億ドル規模の組織が誕生し、NGOのプロフェッショナルとして生きていくには、大きな組織で政策提言やPRや資金調達などで細分化された部署を構え、それぞれの分野の専門人材をプロとしての給与を払って事業を展開する必要があるという主張がありました。本書は、ややアンチテーゼ的な論を展開するもので、21世紀のNGOはアジャイル(俊敏)で現場のニーズへの適応力が高く、現場の知に即して動く必要があるという考えを基調にしていました。現場に近く、人々の声を聞き、即応できなければ存在意義が果たせない、というところに共感し、著者と折衝し、翻訳に関わり、日本に紹介しました。
グローバルな視点から見ると、NGOの世界ですら日本はやはり言葉の問題があって、ガラパゴス化して世界の流れについていけていないところがありました。そこで、国際的な潮流の中で日本も参考にした方が良いことを紹介する活動を自然とするようになり、それは現在の活動にも繋がっています。

2012年10月、世界銀行・IMF年次総会(東京)でキム世銀総裁(右)とラガルドIMF専務理事(左)の市民社会会合で司会進行役を務める(中央)
では、現在今田さんが注力していらっしゃる社会的インパクトマネジメントにはどのようにつながっていったのでしょうか。どのような経緯があったのでしょう。
「ほっとけない世界のまずしさ」キャンペーン後、わたしは、CSOネットワークに在籍しながらも、2007年から2013年まで南アフリカのヨハネスブルクで働いていました。そこで評価の醍醐味に出会いました。
キャンペーン後、その運営のG-CAP(Global Call to Action against Poverty)のグローバル事務局から声がかかり、南アフリカで仕事をすることになりました。1年弱ではじめの仕事は一段落したのですが、その後G-CAPの母体である国際NGOのCIVICUS本体を手伝ってくれないかと声がかかり、事務局次長として仕事を始めました。仕事の一部に、当時はポストMDGsと呼ばれていましたが、現在のSDGsに連なる動きの中で、国連などとの折衝のための市民社会側の意見集約や調整がありました。そういった事業運営の仕事を進めるうえで、評価や社会的インパクトに携わるようになりました。CIVICUSに関わることで、ドナーへのインパクトレポートを求められ、考えざるを得なくなりました。外部評価者には事業運営側から見てとても役に立つ人とぜんぜんこちらのニーズと合致しないことを言ってくる人がいて、事業運営側が評価リテラシーを上げないといけないと痛感し、いろいろと勉強しました。CIVICUSでは5年強働きました。そこでの経験は、その後の日本での評価や社会的インパクト・マネジメントに関わる活動に役立っています。
次回は、社会的インパクトについてより詳しく話してもらいます。今田さんの今後の展望も教えていただきます。どうぞお楽しみに!
聞き手:CSOネットワーク プログラムアソシエイト 山本真穂
プロフィール:

今田 克司(いまた かつじ)
常務理事
(株)ブルー・マーブル・ジャパン代表取締役、(一財)社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ(SIMI)代表理事、(特活)日本評価学会常任理事・研修委員長、(一社)SDGs市民社会ネットワーク理事、(特活)日本NPOセンター理事。
社会的インパクト・マネジメント関連では、2015年内閣府社会的インパクト評価ワーキンググループ委員、2016年度よりSIMI共同事務局メンバー等。2017年度より、CSOネットワークで「発展的評価」研修事業(伴走評価エキスパート事業)、日本NPOセンターで「事業評価コーディネーター」研修事業を開発・主導。SDGs時代における「役に立つ評価」の評価文化やインパクト・マネジメントを根づかせる試みで牽引役を果たしている。
2019年より休眠預金等活用法における指定活用団体である日本民間公益活動連携機構(JANPIA)評価アドバイザー、国際協力機構(JICA)事業評価外部有識者委員会委員。2020年より金融庁・GSG国内諮問委員会共催「インパクト投資に関する勉強会」委員。
講師派遣についてはこちらをご参照ください。