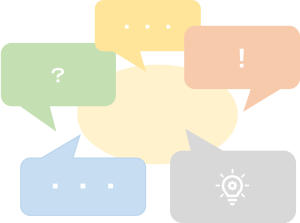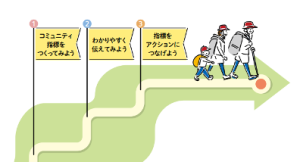CSOネットワーク リサーチフェロー
高木 晶弘
世界的な金融危機による途上国への影響が懸念されるなか、 この危機をむしろチャンスにするべきだという機運が「国際連帯税」などの革新的資金調達メカニズムに関して高まりつつある。 本稿後編では、国際連帯税をめぐり活発化する日本での動き、金融危機と国際連帯税の関係、通貨取引税と今後の展開について、 最新の動向をまとめる。
動き出しつつある日本
日本においては、特に2008年に入ってから、国際連帯税をめぐる動きが活発化した。 2005年後半以降、オルタモンドなどのNGOが取り組みはじめ、 千葉大学などの研究者を巻き込みながら2006年に「グローバル・タックス研究会」が設立され、数多くの勉強会が開催されてきた。 また、北海道洞爺湖サミットに向けて、2008年G8サミットNGOフォーラムの貧困・開発ユニットにおいても、 ワーキンググループが設置されて、政策提言活動を行った。
国政レベルでは、国際連帯税を日本でも創設しようという動きが出て、2008年2月に「国際連帯税創設を求める議員連盟」が超党派で設立された。 同会長には自民党税調のトップである津島雄二議員が就任し、経済や環境に関心を持つ有力な議員も名を連ね、著名なオピニオン・リーダーである寺島実郎氏も勉強会の講師として招かれた。 議員連盟の目的は、日本政府が連帯税リーディング・グループに正式参加すること、「通貨取引開発税(CTDL)」に関する研究を進めること、 そして日本政府がCTDLのタスクフォースを組織してその議長となること、という野心的なものである。 結果として、日本政府は2008年9月にグループに正式加盟し、コナクリ総会に正式メンバーとして参加することになった。
一方、国際連帯税が政府機関内でも認知されたのは、寺島実郎氏の貢献が大きい。 寺島氏は、福田首相(当時)が主催した「地球温暖化問題に関する懇談会」において、温暖化対策のための国際連帯税の重要性を強調した。 その結果、福田ビジョンにおいて、政府として「地球環境税」を検討すると発表され、「地球環境税等研究会」が設置されることになった。 同研究会はすでに2回の研究会を開催しており、来年3月には報告書をまとめる予定である。
このような進展を見せる中で、2008年11月23日、 NGOや研究者を中心とした市民社会の実行委員会が「国際連帯税東京シンポジウム2008~日本での実現をめざして」を主催した。 寺島実郎氏の基調講演につづき、地球環境税等研究会の座長である植田和弘京大教授、同研究会委員の上村雄彦千葉大准教授、 議員連盟幹事長の林芳正議員、同事務局長の犬塚直史議員、外務省の大江博地球規模課題審議官、NGO代表などが結集し、 国際連帯税を日本においてもさらに推進していくための積極的な議論を行った(詳細はこちら )。 同シンポジウム実行委員会は、今後、「国際連帯税推進市民委員会」(仮称)の創設を発表し、来年の春には始動する予定である。
金融危機と国際連帯税

国際連帯税東京シンポジウム2008の様子
昨今の金融危機は、国際連帯税にとってチャンスか否か。 これについては、コナクリ総会においても「東京シンポジウム2008」専門家会合においても議論の対象となった。 財務省の関係者は、金融業界が頻死の状況にあるなかで、さらに金融を規制して課税しようというのは致命傷になりかねないとの懸念を示した。 一方、特に通貨取引税などを推進したいNGOや研究者などは、こういう時だからこそチャンスだと考えている。 通常の状況ならば、世界経済においてあまりにも強大なパワーをもっており、市民社会による通貨取引税導入の提案などに一顧だにしないで済む金融セクターだが、 こういうときだからこそ規制の声に後押しがある、という見方である。 「危機をチャンスに」とはオバマ次期米大統領も環境対策推進論者も唱えており、一方でフランスや英国はポスト・ブレトンウッズ体制を唱えて新しい世界経済秩序を模索しようとしている。新しいシステムが模索されている今だからこそ、新しいイニシアティブを導入する政策機会が生まれていることは確かである。とはいえ、それが通貨取引税として具現化するのかどうかはまだ道半ばであり、今後の市民社会による取り組みも大きなカギを握る。
これを革新的資金調達メカニズムの文脈で考えると、大きく分けて2つの論点が浮上する。 一つは、金融危機をもたらした現在の金融システムの在り方そのものに疑問を投げかけ、公正なグローバル経済のためには金融への規制を強化するべきだという論点である。 もう一つは、先進国経済の停滞によって開発資金の増額への見込みが低くなりつつあることで、革新的なアプローチへの必要性がさらに高まっており、 政府資金援助(ODA)とは異なる手法で、貧困や気候変動などのグローバル・イシューに対処するための資金を調達するメカニズムが必要であるというものだ。
この2つの論点を併せもつのが、「国際連帯税」である。 フランスなどを中心にすでに航空券税として導入されているが、他の課税方法も検討されてきている。 現在の金融危機の文脈では、欧州を中心とした市民社会が従来主張してきた「通貨取引税(CTT)」が議論の中心となりつつある。 通貨取引などの金融取引を課税によって規制するとともに、その税収を再分配することによって、より公正なグローバル経済に近づくのではないかという考えには、現在の世界経済システムを見直すうえでも一定の説得力がある。
通貨取引税
通貨取引税は、主要国の消極姿勢によって、国際連帯税として未だに導入されてはいない。 しかし、技術的には可能だとする主張は多い。 欧州各国のNGOをはじめ、ノーベル経済学賞受賞者であるジョセフ・スティグリッツ教授も可能であると同意している。 また、潜在的な資金調達の規模も大きいのも魅力である。 ノース・サウス・インスティテュート(カナダ)の研究者であるロドニー・シュミットの研究(2007年)によれば、 主要通貨(米ドル・ユーロ、円)で導入した場合、0.005%の税率で、年間約330億ドルの税収を得られる。 OECD開発援助委員会(DAC)諸国の2007年ODA実績は1035億ドルだから、世界のODAの約3分の1をカバーする規模である。 また、ミレニアム開発目標(MDGs)を達成するために必要な追加資金は年間約500億ドルだとされているので、その3分の2に匹敵する規模である。 日本円だけで導入した場合は、同率で年間約56億ドル(約5600億円)が調達可能で、これは日本の2007年ODA実績の76億7900万ドル(約7679億円)の約73%に相当する。
また、これまでの通貨取引税の議論では、投機を抑制するために、2段階課税方式も提案されている。 スパーン税と呼ばれるものだ。 平時の取引には低い税率をかけるが、一定の基準を設けてその基準を超えた場合には非常に高率の税率をかけ、急激な為替相場の変動を抑え込もうという税方式である。 アジア通貨危機を教訓にすれば、この方式は理想的ではあるが、実現可能性という意味では難しくなる発展型である。
日本と世界で活発化しつつある動き
現在、「国際連帯税創設を求める議員連盟」では、フランスの国際連帯税創設に大きく貢献した大統領の諮問機関である「ランドー委員会」の例に倣い、 国内の有識者を集めた「日本版ランドー委員会」を組織しようと検討している。 同委員会では、特に通貨取引税の導入を中心とした国際連帯税の制度設計を検討していく予定であり、NGOや研究者の積極的な提案も期待されている。 一方、国際的にも追い風が吹き始めている。連帯税リーディング・グループにおいても、フランス政府がついに動き出しつつあり、通貨取引税を含む金融取引税の多国間タスクフォースを結成するべく準備を始めた。 来年2月にはその準備会合がパリで行われる予定である。 このことは、元来NGO側がずっと働きかけてきたものであり、その努力がついに実りつつあるということだろう。 日本政府にも積極的な参加を求めたい。
金融システムの見直しが求められる一方、2015年までのMDGs達成への進捗状況に遅れが目立ち、 さらには気候変動対策における途上国支援のために莫大な資金が必要と見込まれるなど、追加的な資金需要も高まるばかりである。 その意味で、「開発資金のための連帯税リーディング・グループ」による取組みや、日本国内の前向きな動きは、ますますその重要性を増してきている。 国際連帯税は、現在はまだ発展途上のイニシアティブであるが、大きな潜在能力と意義を内在している。 市民社会は、実現に向けた数々の難題を乗り越えなくてはならないが、より強力に政府の後押しをしつつ、この議論をさらにリードしていく重要なアクターとしてその存在感を増していくだろう。