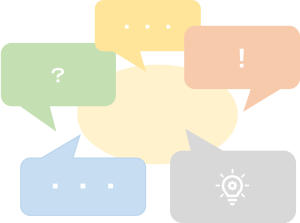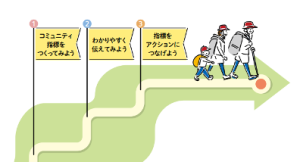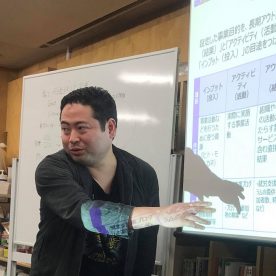「専門性」を探して
私は日本の大学を卒業後、渡米して現地の大学院で国際関係学を修めました。子どもの頃から色々な国に訪れて働きたいという思いがあり、決めた進路でした。中でも東南アジアの国々の歴史や開発に関心があったので、修了後はベトナムの研究機関に就職し、山岳地帯の少数民族コミュニティを対象とする調査でキャリアをスタートさせました。同僚や上司は社会学、人類学、環境サイエンスなどの専門家集団。経験豊かな彼ら彼女らからたくさん学ばせてもらった一方で、国際関係を学んできた自分としては「私の専門性って何?」と悩むことが多かったですね。
その後、JPO制度を通じて国連機関のミャンマー事務所に着任したのですが、私はここでも「何でも屋」的に、緊急支援から農村開発、人身売買やガバナンスの分野の事業を担当しました。その結果、何か一つの専門性がつくどころか、様々な分野の事業でどれも中途半端に経験を積んでしまったところがありました。当時を振り返ると、自分の進むべき道がどこにあるのか見えなくなっていましたね。同じ頃、事務所内では上司の思いつきとしか思えない方針や意思決定の進め方に振り回される悩みも抱えていました。特に事業の設計や運営に関して、本来は受益者を中心にすすめられるべき議論が全く違う力学の中で進められている状況に対し、大きな無力感を感じていました。そんな中、偶然参加した研修で「実用重視のプログラム評価」を提唱していたマイケル・クィン・パットン氏と出会いました。
「評価を使いこなせるようになれば、きちんと根拠を示し、上司の思いつきの意思決定に立ち向かえる。本当に役立つプログラムを実施できるようになるのではないか」。研修が進むにつれ、目から鱗が落ちる思いでした。それからは、プログラム評価の考え方やスキルを懸命に学ぶ日々でした。このパットン氏との出会いによって、私は「調査」から本格的な「評価」の世界へ、それも現実とどう向き合うかという評価へと足を踏み入れたと思います。
机上の手法と複雑な現実
ただ、実際に評価を実践しようとすると、その壁は思った以上に高かったですね。初めて自ら立てたプログラム評価の企画が通り、はりきって準備したのですが、いよいよヒアリングという段になると困惑しました。村の幹部の男性だけがずっと話し続け、女性が誰ひとり出てこない。評価対象が母子プログラムであったにもかかわらず、です。
当時のミャンマーでは、村に外国人が訪れること自体が大ごとだったという背景もありました。軍事政権下で、もともと自由にものが言える状況でもない。私も村の人々も腹の探り合いで、互いに忖度し、実際のプログラムの状況をきちんと検証することは非常に難しいのが現実でした。仕事をすればするほど、現場にある現実が複雑すぎて、玉ねぎの皮を永遠に剥いているような感覚を覚えました。評価の基本は「事実特定と価値判断」ですが、当時はこうして調査をしても、いったい事実が「何」なのか特定することはとても難しかったのです。玉ねぎの皮を剥いても剥いても、どれも事実である気がするし、全部違うようにも思えてきます。例えば、現地の地域保健センター等で記録されたデータの結果が良かったからといって、「事業は有効だった」で終わってしまっていいのだろうか。現場の村人たちの個人の実感としてどうなのか。当事者たちの実感を無視して「これがエビデンスだから」と言えるのか…。当時の私は、発展的評価を知りませんでした。ですから、こうした複雑な状況においても、藁にもすがる思いで単線的なロジックモデルに頼らざるを得ない評価を実施していたのです。
発展的評価との出会いは、私にとって2度目となるパットン氏の研修でした。CSOネットワークの今田さんと出会い、そのつながりから参加することになったのですが、従来型の評価に限界を感じつつも、「評価はこういうものだから」と半ばあきらめも交じりながら実践をくりかえし悩んでいた私にとって、大きな転換点となりました。
レフ版をもつ評価者
評価者に大切な資質は、事業で「どういうよい成果が出るか?」に加え「どういう悪影響が出るか?」という視点をもつことだと私は考えています。評価者は、中立的でありながらも、プログラムによって様々な受益者が「困らないか」を考える役割を担っています。と言っても、対象コミュニティがみな困らないようにする、という単純な構図ではありません。マイノリティの中でも、強者と弱者はいるからです。諸条件により前者はプログラムを活用できる、つまり介入によってよい方に変化できますが、後者はそうではない。そうなると、コミュニティの分断を生んだり、弱者へのスティグマを誘発したりする可能性があります。
現実には、どんなプログラムでも負の影響は避けられません。その負の影響を全て把握するために、評価調査が最弱者にアクセスできるというのも幻想でしょう。だからこそ、想像力を働かせて、負の影響を最小限にとどめるよう手綱を取るのも評価者の大切な役割だと私は思っています。
プログラムは介入です。現場の人々にとっては、ある意味「とばっちり」。だから、プログラムを実施する側には、人の人生に影響を及ぼすことの責任があります。これは公/民を問わず言えることです。そして評価者は、いわばレフ版を持ちながら、プログラムの様々な側面に光を照射させ、プログラムが実施すること、実施したことが何かを明らかにし、説明責任を果たす役割を担うべきと考えています。
こう言うと、プログラムで「介入」すること自体が否定的に聞こえたかもしれませんが、問題を抱えたところに「外部」が入ってくるのは、基本的にはよいことだと私は思っています。問題を閉じた場所に置くのではなく、公(おおやけ)の場に引っ張り出し、介入という「ひっかきまわし」を受けて回復する力、その過程で発揮される新しい力、それらがやはり介入によって引き出される場面をこれまで目の当たりにしてきたからです。
仕事を始めたころは「自分のセクターはどこか?専門は何か?」と悩みましたが、今では「素人」として多種多様な事業に関われる評価者の役割が気に入っています。現場にずんずん入る、ひたすら聴く、誰もがわかるように説明する。そうしたレフ版を持つ評価者という役割を、これからも丁寧に果たしていきたいと思います。評価者として「最強の素人」を目指したいですね。
(聞き手:事務局 清水みゆき)